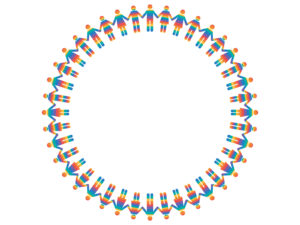多様性とリーダーシップ(女性活躍の観点から)
花のない桜を見上げて
満開の時を思ったことがあったか?
どうせ無理だとあきらめず、一人ひとりが小さな挑戦を積み重ねながら、
多様なメンバーが活き活きと躍動する未来を信じる。
その眼差しの中に、日本企業躍進の大きなヒントがあるように思います。
本コラムでは、「多様性」の中でも特に「女性活躍」に焦点をあてます。
1.歴史の影と現在の転換点
日本は戦後、欧米の背中を追いかけて高度経済成長を遂げました。
しかし1990年代初頭のバブル崩壊後、復活のきっかけをつかめないまま停滞の30年を経験しています。
この時代を生きた一人として、これからの飛躍を願わずにはいられません。
ところで、性別の多様性が組織の集団知能1)、業績、イノベーション力を高めることについては、
様々な研究結果があります。
一方、これらを実現するためには、「多様性(ダイバーシティ)」だけでなく
「包摂(インクルージョン)」にも注目する必要があります。
•ダイバーシティ : 多様な人が「いる」こと
•インクルージョン: 多様な人が「活躍できる」こと
特に後者を実現するためには、次の二点が鍵となるでしょう。
(1) 活躍を妨げる障壁を取り除くこと
(2) 各自が活躍への意識を高めてリーダーシップを発揮し、周囲は支援すること
2.日本社会に埋め込まれた無意識の壁と社会制度の変化
明治以降、「女性は家庭を支え、子を育てることが使命」という価値観が教育や
社会制度に組み込まれました。
この歴史的背景から、「女性のあるべき姿」という
『アンコンシャス・バイアス(無意識の偏見)』が生まれ、
今でも根強く残っています。
しかし時代は変わり、社会や企業は女性の働き方を支援する方向へ舵を切りました。
流れは次のように移り変わっています。
•「働く権利の獲得」→「働き続けられる環境の整備」→「リーダーシップ発揮の場の構築」
政府も、男女雇用機会均等法(1986)や育児・介護休業法(1992)等の制定を通じて、
女性活躍の障壁を取り除いてきました。特に、女性活躍推進法(2016、2019改正)では、
企業に女性管理職比率や採用比率の数値目標を立てたうえで、
それを開示することを求めています(但し、具体的数値設定は企業に一任)。
3.今につながる「あの時代」の活躍
「女性は家庭に専念する」そういった考えが社会に強くあった時代の中で、
明治・大正期から「平塚らいてう」ら女性運動家は「個性の尊重」「自己実現」を訴えました。
市井の女性たちも、茶道や華道、編み物や洋裁、地域活動(婦人会・PTA)、
子育て(教育方針の決定や習い事の選択)といった場で「非公式な自己実現」を果たしていました。
私自身、母(昭和9年生まれ)が洋裁教室で仲間に無償で教える姿を覚えています。
まだ私が小さく、幼稚園から小学校低学年の頃でした。母親同士で週に一回集まり、
わいわいがやがや、本当に活き活きと楽しそうでした。それは社会とのつながりを持ち、
自分の能力を発揮しながら存在意義を確認する、大切な場だったのだと思います。
4.いま巡ってきたチャンスとリーダーシップの発揮
社会も会社も、ダイバーシティとインクルージョンを積極的に進めようとしています。
働きながら自己実現する大きなチャンスです。
•プレーヤーとして成果を上げる
•リーダーとして新しいチームを築く
その方法は人それぞれです。皆さんのチャレンジを後押しする土壌は整ってきました。
とはいえ、現場では壁にぶつかり、心が折れそうになることもあるでしょう。
「女性活躍」の旗印の下で、パイオニアとして重荷を担わされることもあるかもしれません。
周囲の理解が追いつかず、孤独を感じる場面もあるでしょう。
でも、それでも、各自が躍動する場を創れるかどうか、それは一人ひとりの挑戦にかかっています。
「私には無理かも」という『アンコンシャス・バイアス』に囚われず、自分の考え方や行動を変える
勇気も必要です。
環境は整った。いよいよ変革を起こすのは、皆さんの挑戦です。
挑戦する皆さんを、私たちは全力で応援します!!
【参考文献】
1) Evidence for a Collective Intelligence Factor in the Performance of Human Groups, Anita Williams Woolley, Science 330 et al. , 686 (2010); DOI: 10.1126/science.1193147
- 2025/08/28
- コンサルティング
- 投稿者:講師 河野 貴史